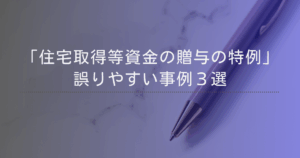税務調査の当日はどんな流れになるのか?
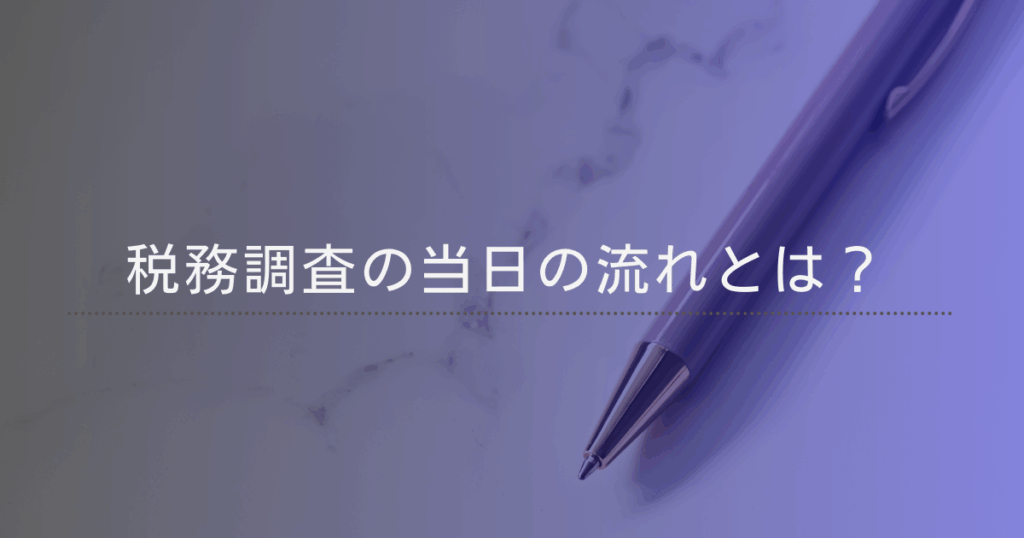
こんにちは。兵庫県明石市のひとり税理士、平太誠です。
税務調査は、通常、事前に「調査を行う旨の通知」があります。
しかし、当日の様子がわからないということで不安を感じる方も多いかと思います。
今回は、税務調査当日の流れを時系列でご紹介し、安心して対応できるようポイントを解説します。
税務調査当日の流れ
① 税務署職員の来訪
調査当日は、事前に連絡のあった時間に税務署の職員(通常は2名程度)が来訪します。
調査場所は事前に指定されますが、一般的には事業を行っている事業所で調査が行われます。
まずは調査官から身分証を提示されますので、職員であることをしっかり確認しましょう。
② 質問とヒアリング(事業内容の確認)
挨拶を終えた後、いきなり調査開始というわけでもなく、雑談のような会話からスタートします。
調査官の器量にもよりますが、雑談から得られる情報とういうのは意外と多いものです。
「なんか雑談長いな……」と感じたら、やり手の調査官が来たなと思っていいかもしれません。
ひと通り雑談をした後、続いて、調査官は「いまどんな事業をされていますか?」という感じで事業についてのヒアリングが開始されます。
このあたりから、いよいよ調査が始まったなと感じるのではないでしょうか。
聞かれるのは例えば以下のようなことです:
・主な事業内容・業種
・取引先の構成(法人・個人・地域など)
・取引の流れ(例:商品仕入れ~販売まで)
・経費の使い方、日常の管理方法
・現金や預金の取り扱い状況
ここでは、「もの・人・お金の流れ」をしっかりと確認することが目的です。
申告内容との整合性を確認しながら、「聞き取り」という形で確認していきます。
なお、細かい経理の流れについて、経理担当者でないと分からないという場合には、経理担当者を同席させることも検討しましょう。
③帳簿・証憑書類の確認
ヒアリングが終わると、実際の帳簿や領収書、請求書、通帳などの確認に入ります。
一般的には次のような資料を提示できるようにしておきます。
・総勘定元帳や仕訳帳
・売上・仕入帳、請求書・領収書
・預金通帳
・クレジットカード明細
・経費の領収書
・その他事業に関連する資料
チェックされるのは、以下のような点です:
・売上の除外や計上漏れがないか
・経費の内容が業務に関係しているか
・領収書や請求書の整合性
・現金の出入りに不審な点がないか
④ 口頭での質問対応
帳簿確認中に、調査官は気になった点を都度質問してきます。
書類上だけでは内容が分からない支出や取引内容について、実態を把握するために行われるものです。
たとえば次のような質問がされることがあります:
「この支出は具体的に何に使ったのですか?」
「この取引先とはどういう関係ですか?」
「現金をこの日に引き出していますが、使い道は記録していますか?」
質問に対しては、可能な限り正確に、具体的に答えることが大切です。
ただし、その場でよく思い出せない場合は、無理に回答せず、「記録を確認して後日お答えします」と伝えて構いません。
また、調査官は会話の中で得られた情報をメモとして残していきます。
これらのメモは、調査後の整理資料や指摘事項の判断材料として使用されるため、回答内容には慎重さも求められます。
答える際のポイント
・「だいたい○○くらいだったと思います」といった曖昧な表現は避ける
・質問の意図が不明な場合は、内容を聞き返して確認する
・私的な支出に関する指摘があった場合は、事実を正直に説明する
調査官はあくまで事実の確認をしたいだけなので、変に隠したり取り繕ったりしない方が良い印象になります。
また、もしも調査官の見解に違和感や疑問を感じた場合は、その場で無理に反論する必要はありません。
冷静に話を聞いたうえで、後日、顧問税理士等と相談して対応方針を決めるのが得策です。
⑤ 当日のまとめと今後に関する説明
調査の終盤になると、当日確認した内容のまとめや、今後の流れが説明されます。
一部確認できなかった資料については、データでの提供やコピーを依頼されることがあります。
また、資料を税務署に持ち帰ってもいいかを尋ねられることもあります。
当日の調査を終えた後、調査官が署内で検討し、追加の質問などを経て、調査結果をまとめていきます。
なお、調査官が来訪する、いわゆる実地調査は1日で完了するケースもありますが、数日間に分けて実施される場合もあります。
まとめ
税務調査は、「不正を暴く」ためのものではなく、「申告が正しく行われているか確認する」ための手続きです。
当日は、
・調査官の来訪・挨拶
・事業のヒアリング
・帳簿・証憑の確認
・口頭質問
・今後の案内
という流れで進んでいきます。
事前にしっかり準備をし、冷静に対応すれば、必要以上に恐れる必要はありません。
免責事項
- 内容については、執筆時点の法令等に基づき記載しているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 正確性等を高めるよう努めておりますが、当ブログに記載された情報をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。