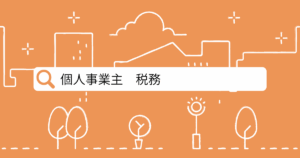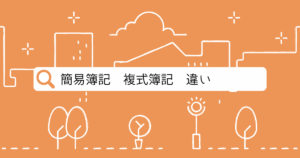NISA、iDeCo、小規模企業共済…優先順位は?
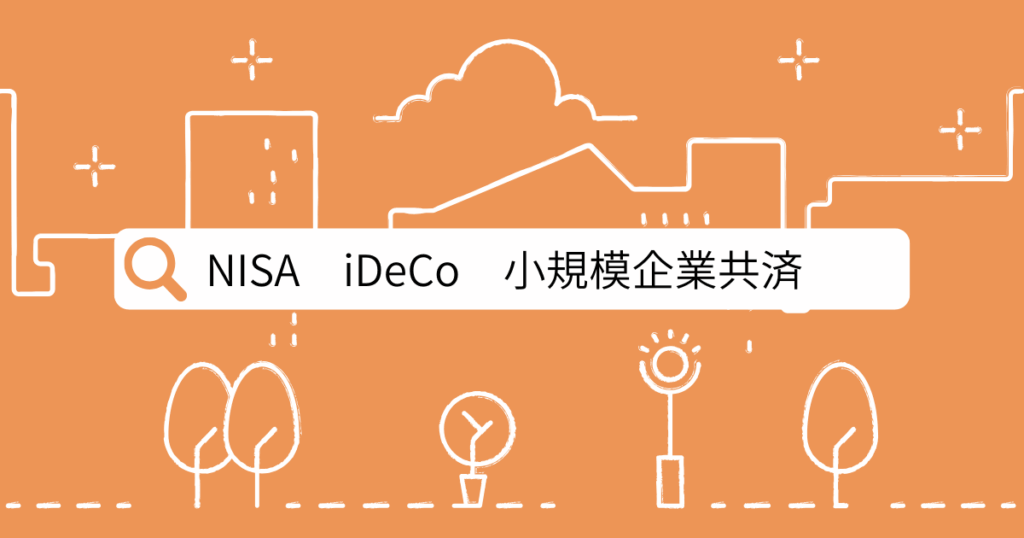
こんにちは。兵庫県明石市の税理士、平太誠です。
個人事業主のお金の運用について、代表的なものでNISAがあります。
他に人気なのは小規模企業共済やiDeCoです。
これらは節税対策の視点もあります。
それぞれどのような特徴があるのか、そして、優先順位はあるのか。
NISAの特徴
NISAとは、購入した株の運用で得られる配当や売却益について非課税になる制度です。
2024年から新NISAとして生まれ変わりました。
非課税期間の恒久化、年間の投資上限額の変更などがありました。
投資限度額は、生涯1,800万円(年間では360万円まで)です。
株式投資はもちろんリスクを伴うものですが、投資信託などリスクが少ない商品もあり、とても人気です。
銀行に預けているよりは全然良いと考えられ、多く方が利用しています。(2025年3月末:約2,500万口座)
特徴としては、すぐに辞められるということがあります。
NISAは長期投資が基本なので辞めるのはもったいないのですが。
どうしてもお金が必要になった場合には仕方がありません。適宜のタイミングで株を売って換金できます。
また、投資額に対して節税効果などはありませんが、受取り時の利益・配当は全て非課税です。
iDeCoの特徴
iDeCoは、年金に上乗せできる私的年金制度です。老後の蓄えを増やすための制度です。
運用方法は、NISAと基本的には同じ。
自分で金融商品を選んで、投資します。
商品の運用成果次第で将来受け取れる金額が変わってきます。
なお、運用益は非課税です。
特徴としては、原則60歳まで引き出せないものになります。
年金と同じく、長期にわたって資金が拘束されます。
また、投資した掛金が税金計算上の控除となり、節税効果があります。
ここも国民年金制度と同じということです。
将来受け取る時には年金形式又は退職金形式かを選択します。
受け取る金額によっては課税されることもありますが、いずれにしても税制上は優遇されています。
小規模企業共済の特徴
小規模企業共済とは、個人事業主のための退職金制度です。
個人事業主は基本的に退職金というものがありませんので、その代わりに設けられた制度です。
毎月1,000円~7万円までの範囲で自由に設定できます。
特徴として、基本的には廃業時までは受け取ることができません。途中解約すると、元本割れのリスクがあります。
また、貸付制度があり、掛金の範囲内で融資を受けることができます。
さらに、iDeCoと同じく、掛金に対して所得控除があり、節税効果があります。
受け取る時には年金形式又は、退職金形式かを選択します。こちらもiDeCoと同じです。
金額によって課税されることもありますが、いずれにしても税制上は優遇されています。
どれを優先すべきか
それぞれの特徴について、まとめると
NISA:投資の自由度が高い。換金自由度も高い。
iDeCo:掛金が所得控除されるので節税効果がある。老後資金用のため資金が長期拘束される。
小規模企業共済:事業者の退職金制度。貸付制度あり。所得控除による節税効果あり。ただし長期継続が前提。
優先順位については、それぞれの立場や考え方によって様々ではあります。
個人的には、NISA→小規模企業共済→iDeCoで良いかと思います。
NISAは資金の自由度がありますので、基本的に困ることはありません。
NISAの枠が一杯になって、資金が余っているのであれば小規模企業共済も利用します。
小規模企業共済は資金が拘束されますが、いざという時は借入制度がありますのでひとまず安心です。
さらに資金が余っているようならiDeCoで老後資金の積み立て+節税効果を狙うといった感じでしょうか。
とにかく節税を!と考えて、まず小規模企業共済とiDeCoに満額投資するのも良いですが、資金が拘束されるということは念頭に置いておきましょう。
免責事項
- 内容については、執筆時点の法令等に基づき記載しているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 正確性等を高めるよう努めておりますが、当ブログに記載された情報をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。