社会保険料をどう抑えるか
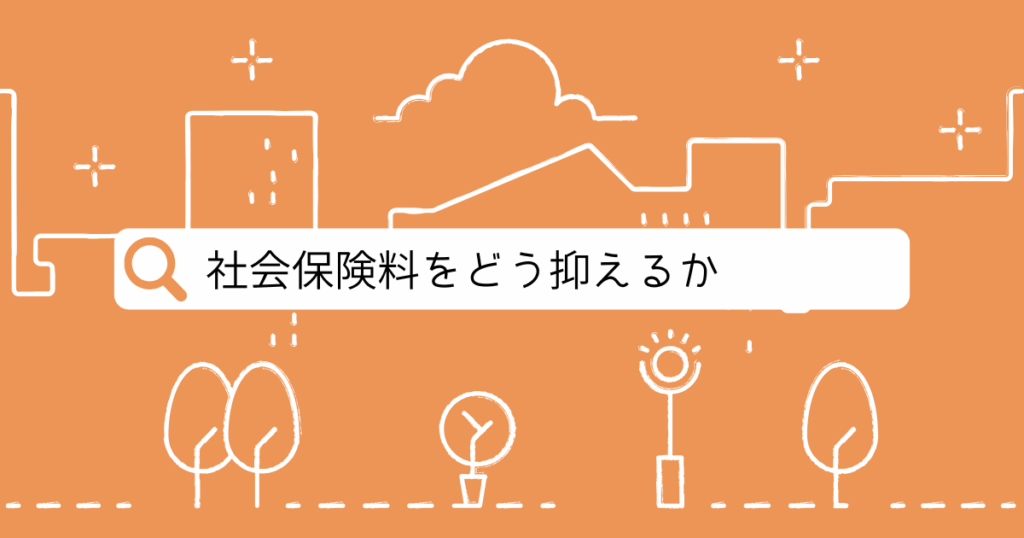
こんにちは。兵庫県明石市の税理士、平太誠です。
個人事業主の悩みのひとつとして、社会保険料高すぎ問題というのがあります。
社会保険料というのは選択肢がひとつではなく、いろいろと選択肢があり、検討の余地があります。
どうやって抑えるのが正しいのでしょうか。
個人事業主が支払う社会保険料とは
まず、個人事業主が負担する社会保険は、主に健康保険と国民年金があります。
会社員の方も払っているもので、会社員なら給与から天引き、個人事業主は自分で支払い手続きをします。
大きな違いは2点あり、1点目は、会社員は会社と折半で支払うのに対して、個人事業主の場合は全額負担です。
2点目は、「扶養家族」の取扱いです。
会社員の場合、扶養の範囲内であれば扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
個人事業主の場合、「扶養家族」という概念がなく、人数分の負担があります。
健康保険料を抑えられるか検討する
年金保険料は固定額ですが、健康保険は加入団体によって保険料が変わります。
個人事業主の場合、一般的には国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険とは、「会社を辞めたら加入しましょう」と案内される市区町村の健康保険のことです。
ただ必ずここに加入しなければならない訳ではありません。
選択肢①:業界の健康保険組合
一部の業種については、個人事業主であっても健康保険組合に加入できることがあります。
健康保険組合がある業種は、建築、土木や税理士、医師、文芸、美術関係など。
市区町村の健康保険との違いは、保険料の計算。
市区町村の健康保険が収入に応じて保険料が計算されるのに対して、健康保険組合は1か月あたりの固定額になっていることが多いです、
収入(所得)が多くなってくると国民健康保険に加入するより安くなるケースが多いため、検討する余地があります。
自身の業種にはどんな健康保険組合が存在するのか、ネットで調べたり同業者に聞いてみましょう。
選択肢②:退職した会社の任意継続
退職後すぐに国民健康保険に切り替えるのではなく、会社の保険を継続することで一定期間は保険料を抑えられることが多いです。
ただし退職時期や退職後の年収、家族構成などによって変わりますので、シミュレーションは必要です。
ちなみに2年間は継続しなければならないと言われてますが、保険料を支払わなければ強制的に脱退させられます。
社会保険料削減スキームについて
ネット広告などで、「個人事業主・フリーランスの方の社会保険料を削減します!」と謳っている広告が多数あります。
運営元は一般社団法人○○協会などが多いようです。
どういう仕組みなのか。
調べてみたところ、依頼者が運営元の法人の理事になって、報酬をもらうといった形を取るようです。
要は、この運営元の理事として働くことで、個人事業主でありながら、会社員と同様の社会保険に加入することができ、保険料を大幅に削減できるということです。
法律上はOKなのでしょうが、名前だけ在籍している理事ということになり、実態を伴っていない点が気になります。
(実態を無理やり作るために1か月に1回ほど会議みたいなものに出席するらしいですが……。)
後になってひっくり返されるリスクがあり、手をださないのが無難だと思います。
また、個人情報が洩れてしまう危険性があることも注意が必要です。
免責事項
- 内容については、執筆時点の法令等に基づき記載しているため、記載内容が必ずしも最新の情報であるとは限りません。
- 正確性等を高めるよう努めておりますが、当ブログに記載された情報をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、必ず顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。

